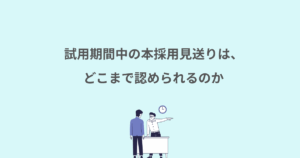労働条件通知書の役割とは?
― 法律が「入社前の条件明示」を求める理由 ―
採用の場面では、
「まずはこの条件で」「細かい点は入社後に調整する」
といったやり取りが行われることがあります。
人手不足や業務の忙しさを考えれば、
こうした判断自体が現実的な場面も少なくありません。
しかし、労務トラブルの多くは、
その「後で調整するはずだった条件」が、契約内容として整理されていなかったことをきっかけに生じています。
労働条件通知書は、
こうしたズレを防ぐために、
法律上、明確な位置づけを持つ書類です。
もくじ
入社前の条件提示は「説明」ではなく「契約内容の確定」
入社前のやり取りは、
条件を説明する場面だと捉えられがちです。
しかし、法的に見ると、
この段階で行われているのは
労働契約の内容を確定させる行為です。
- どこで働くのか
- どの業務を担当するのか
- いつ、どの時間帯で働くのか
- 賃金はいくらで、どのように支払われるのか
これらは、
「働き始めてから決めること」が前提の事項ではありません。
労働契約は口頭でも成立する
労働契約は、
労働契約法第6条に定められているとおり、
労働者と使用者の合意によって成立する契約です。
この合意は、
必ずしも書面で交わされなければならないものではなく、
口頭であっても労働契約自体は成立します。
実務上も、
書面が作成されていなくても、
労働契約の成立自体が否定されることはありません。
それでも「形に残すこと」が求められる理由
法一方で、労働契約法第3条では、
労働契約は労働者と使用者が
対等の立場における合意に基づいて締結すべきものとされています。
口頭のやり取りだけでは、
どの条件について合意があったのか、
その内容が後から曖昧になりやすいのが実務上の現実です。
そこで、労働基準法第15条は、
労働契約の締結にあたり、
使用者に対し労働条件を明示する義務を課しています。
労働条件通知書は、
この明示義務を果たすための書面であり、
口頭で成立した労働契約の内容を、形として残す役割を担っています。
労働条件通知書の法的な位置づけ
労働条件通知書は、
任意で作成する社内書類ではありません。
労働基準法第15条および
労働基準法施行規則第5条では、
明示すべき労働条件が具体的に定められており、
その中には書面での明示が義務付けられている事項が含まれます。
労働条件通知書は、
この法律上の明示義務を果たすための
法定文書です。
雇用契約書との違いを整理しておく
多経営者の方とお話ししていると、
「雇用契約書を作っているから問題ない」
と考えられているケースも少なくありません。
ここでは、言葉の整理が必要です。
労働条件通知書
- 労働基準法第15条に基づく法定の明示義務
- 使用者が労働条件を明示するための書面
- 一定の事項については、書面での明示が必須
雇用契約書
- 労使双方が契約内容を確認し、合意するための契約書
- 法律上、必ず作成しなければならないと明記されているわけではない
- 実務上は、労働条件通知書を兼ねる形で作成されることが多い
最近では、
**「雇用契約書兼労働条件通知書」**という形式で作成している企業も多く見られます。
ただし、書類の名称にかかわらず、
内容が法定の明示事項を満たしているかどうかが重要です。
労働条件通知書に記載すべき「絶対的記載事項」
労働基準法施行規則第5条では、
必ず明示しなければならない事項
(いわゆる絶対的記載事項)が定められています。
主なものは以下のとおりです。
- 労働契約の期間
- 就業の場所および従事すべき業務
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日および支払日
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらは、
「重要だから記載しておくとよい事項」ではなく、
記載しなければ法令違反となる事項です。
令和6年4月の法改正が示している方向性
令和6年4月から、
労働条件の明示ルールについて見直しが行われています。
この改正により、
- 就業場所・業務内容について
「雇入れ直後」だけでなく「変更の範囲」まで明示すること - 有期契約の場合には、
更新上限や無期転換に関する事項を明示すること
が求められるようになりました。
この改正は、
単に記載事項を増やしたものではありません。
後から争点になりやすい条件について、
入社時点で明確にしておくことを、法律がより強く求めている
という方向性を示しています。
実務で問われやすいのは「条件をどう整理していたか」
労務相談の現場では、
「書いていないこと」そのものが問題になるというよりも、
入社時に、条件をどこまで整理し、共有していたかが問われます。
たとえば、次のようなケースです。
- 想定していなかった業務を指示された
- 勤務地が変わる可能性について説明を受けていなかった
- 契約更新がある前提だと思っていたが、書面上は明確でなかった
これらはいずれも、
「説明した・していない」という話では終わりません。
労働条件通知書に、
どのような条件が、どこまで具体的に整理されていたかが、
後から判断の基準になります。
曖昧なままにされていた条件ほど、
実務では争点になりやすいのが現実です。
労働条件通知書は「運用判断の土台」になる
労働条件通知書は、
トラブルが起きたときだけ取り出すための書類ではありません。
実務上はむしろ、
- 想定外の業務を依頼する必要が生じたとき
- 勤務地や勤務形態の見直しを検討するとき
- 個別の例外対応を認めるか判断するとき
といった場面で、
**「そもそも、どこまでを前提として合意していたのか」**を確認するために参照されます。
このとき基準になるのは、
記憶や認識ではなく、
入社時に明示されていた労働条件の内容です。
労働条件通知書は、
使用者が一方的に条件を決めるための書類ではなく、
後からの判断や運用を行う際の“土台”を示すものとして機能します。
その意味で、
「念のために交付しておく書類」という位置づけでは、
労働条件通知書が本来持つ役割を十分に活かしているとは言えません。
まとめ
- 労働契約は、労働契約法第6条のとおり、口頭であっても成立します。
- しかし、入社時の条件が曖昧なままでは、後から判断に迷う場面が必ず生じます。
- 労働基準法第15条は、そうしたズレを防ぐために、使用者に労働条件の明示義務を課しています。
- 労働条件通知書は、この明示義務を果たすための法定文書であり、単なる形式的な書類ではありません。
- 入社時にどこまで条件を整理し、共有していたかが、後の運用や判断の基準になります。
労働条件通知書は、
「念のために交付する書類」ではなく、
採用後の運用を支えるための土台となる書類です。
入社前の条件提示が、
法律に沿った形で整理されているか。
その確認が、結果的に不要なトラブルを防ぎ、
無理のない労務運用につながります。