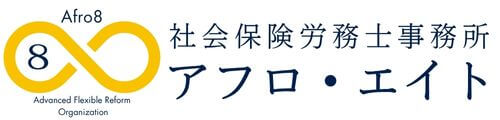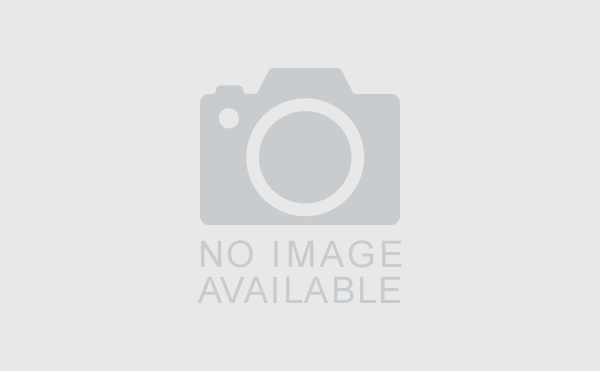2025年10月1日施行 労働法改正まとめと企業リスク~中小企業経営者・人事労務担当者が押さえておきたいポイント~

労働法は社会の変化にあわせ、ほぼ毎年のように改正が行われています。2025年10月1日から施行される改正は、中小企業にも直接影響する内容が含まれています。
私(社会保険労務士)自身も顧問先から
「就業規則は改正に対応しなければいけないのか?」
「従業員にどう説明すればいいのか?」
といった相談を多数いただいています。
この記事では、2025年10月1日に施行される改正のポイントを条文に基づいて整理し、対応を怠った場合のリスク、そして中小企業が今すぐ取るべき実務対応について解説します。
📑 目次
育児・介護休業法の改正
(1) 残業免除の対象拡大
- 改正前:3歳未満の子を養育する労働者のみ対象
- 改正後:小学校就学前までに拡大
- 根 拠:育児・介護休業法 第17条第1項
事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者から請求があった場合、時間外労働をさせてはならない。
(育児・介護休業法 第17条第1項)
📌 対象となる「養育する労働者」について
ここでいう「養育する労働者」には、母親だけでなく父親も含まれます。実際に育児を担っている労働者であれば性別を問わず対象となります。たとえば父親が「保育園の送迎があるため残業できない」と請求した場合も、会社は免除に応じなければなりません。
ある飲食店では、保育園児を持つ社員が「残業できない」と主張し、シフト調整が難航しました。改正後は就学前の子を養育する従業員(父母問わず)が対象となり、代替要員確保が大きな課題になります。
(2) 短時間勤務制度の代替措置に「テレワーク」追加
- 改正前:短時間勤務・フレックス・始終業変更
- 改正後:テレワーク(在宅勤務)も選択肢に追加
- 根拠:同法 第23条の3、施行規則第71条の2
テレワークを導入していない企業は「制度として就業規則に記載が必要か?」というご相談をよくいただきます。
就業規則上で制度選択肢として整備しておくことが望ましく、規模の小さい企業でも“在宅勤務の検討実績”が求められる点に注意が必要です。
(3) 個別意向聴取・配慮義務
- 改正後:3歳以上~就学前の子を養育する労働者に対し、意向を確認し、配慮する義務
- 根拠:同法 第24条の2
📌 企業が行うべき具体的対応
意向の確認例
- 残業免除を希望するか
- 短時間勤務・フレックス・テレワークのどれを希望するか
- 勤務時間・日数の制約があるか
- 育児と仕事の両立で困っていることは何か
配慮の方法例
- 希望制度の利用が可能かを検討する
- 難しい場合は理由を説明し、代替措置を提示する
- 面談記録を残し、後から「聞いてもらえなかった」と言われないようにする
「形式的にヒアリングした」だけでは不十分で、記録を残しておくことが重要です。実際に労基署の調査では「制度はあるが、実際に運用されていない」と指摘されるケースがあります。
高年齢者雇用安定法の改正
- 改正後:給付率が最大15% → 最大10%に縮小
- 根拠:雇用保険法施行規則 第100条の2
60歳以降の就業継続は「戦力維持」と「人件費負担」のバランスが課題です。今回の縮小により従業員から「給付金が減った」と不満が出る可能性もあり、企業側は説明責任を果たす準備が必要です。
労働安全衛生法の改正
対象:常時50人以上の労働者を使用する事業場
対象手続き:
- 定期健康診断結果報告(安衛法 第66条、第52条の2)
- ストレスチェック実施結果報告(安衛法 第66条の10)
従業員50人未満の事業場は報告義務自体がないため、電子申請義務化の対象外です。ただし、今後50人以上になる可能性がある企業は早めの準備が必要です。2025年10月以降は紙提出が認められず、未提出=法令違反となります。
- 行政指導・罰則
健康診断結果やストレスチェック報告を提出しないと、安衛法第120条により50万円以下の罰金の対象。 - 従業員トラブル
「制度を使わせてもらえない」と労基署に申告され、紛争や企業イメージ低下につながる。 - 人材確保・定着への影響
法改正に無関心な会社は「従業員を大切にしていない」と見られ、採用・定着にマイナス。
- 行政指導・罰則
健康診断結果やストレスチェック報告を提出しないと、安衛法第120条により50万円以下の罰金の対象。 - 従業員トラブル
「制度を使わせてもらえない」と労基署に申告され、紛争や企業イメージ低下につながる。 - 人材確保・定着への影響
法改正に無関心な会社は「従業員を大切にしていない」と見られ、採用・定着にマイナス。
法改正に未対応の企業が直面するリスク
各法律ごとのリスク
(1) 育児・介護休業法関連
- リスク:「制度を使わせてもらえない」と従業員から労基署に申告され、是正勧告や企業イメージの毀損につながる
- 具体例:残業免除請求を断った、意向聴取を形骸化した。
(2) 高年齢者雇用安定法関連
- リスク:給付金縮小に伴う従業員からの不満やトラブル
- 具体例:「説明がなかった」と苦情が寄せられ、労務トラブルに発展
(3) 労働安全衛生法関連
- リスク:定期健診結果やストレスチェック報告を提出しないと、安衛法第120条により50万円以下の罰金
- 具体例:常時50人以上の事業場で紙提出のまま放置 → 行政指導+罰則
企業が今すぐ取るべき対応
- 就業規則の改訂(残業免除・テレワーク規定の追加)
- 従業員への説明会・意向聴取の記録化
- 勤怠管理・電子申請システム導入
- 助成金活用(両立支援等助成金など)
まとめ
2025年10月1日の労働法改正は、中小企業にとっても避けて通れないものです。「まだ規模が小さいから大丈夫」と思っていると、思わぬトラブルや行政指導に直結します。
改正対応は単なる法令順守ではなく、企業のリスク管理と信頼獲得につながる経営課題です。御社の就業規則・制度は改正に対応できていますか?
当事務所では、就業規則改訂や助成金活用の支援を行っています。お気軽にご相談ください。